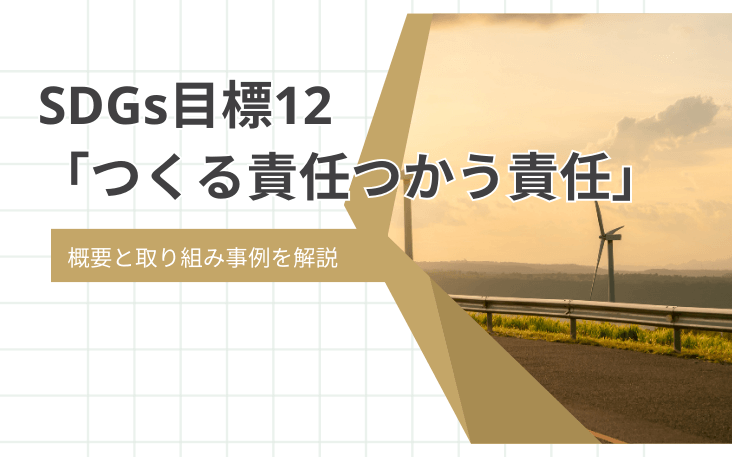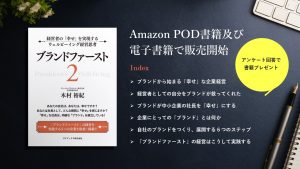SDGs目標12「つくる責任つかう責任」は、生産者である企業と消費者である個人のそれぞれがもつ責任について深く言及した達成目標です。そのため自身の企業や在籍する職場でも取り組みたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
SDGsの理念は世界の共通認識として確立されていますが、実際に活動を始めるにあたって具体的に何をどのようにすれば貢献できるのか迷いますよね。自身の企業や職場でSDGs目標12に取り組む場合、概要やターゲットを理解して、他社の取り組みを参考にするのが有効です。
そこで本記事では、SDGs目標12に取り組む上で参考となる、概要やターゲット、企業の取り組み事例を詳しく解説しました。
本記事を読むことで、自分たちにできることのイメージが膨らみ、具体的な行動に落とし込めるでしょう。ぜひ最後まで読んでいただき、具体的な活動の参考にしてみてください。
この記事でわかること
- SDGs目標12「つくる責任つかう責任」の概要やターゲット
- SDGs目標12に関する企業の取り組み事例
- SDGs目標12に関する世界の現状や私たちにできること
こんな人におすすめです
- SDGs目標12に関する概要や現状を詳しく知りたい方
- SDGs目標12に関する企業の取り組み事例を参考にしたい方
- SDGs目標12を自身の職場で取り組みたい方
目次 [show]
SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とは

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とは、地球の資源を守り、持続可能な生産と消費のバランスを構築するための目標です。この目標は世界の共通認識であり、地球の限りある資源やエネルギーを次世代につないでいくために掲げられました。
SDGs目標12「つくる責任つかう責任」は、つくる側である生産者と、つかう側である消費者の双方に責任があることを示しています。過剰に物を生産したり消費すると、エネルギー資源の枯渇や廃棄物の増加、食品ロスなどの問題につながります。
このような問題に対処するために掲げられたのが、SDGs目標12「つくる責任つかう責任」です。SDGs目標12の達成目標と具体的な対策(ターゲット)は以下のとおりです。
SDGs目標12のターゲット(8つの目標と3つの対策)
| 12.1 | 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 |
| 12.2 | 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 |
| 12.3 | 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。 |
| 12.4 | 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物資質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 |
| 12.5 | 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 |
| 12.6 | 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 |
| 12.7 | 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 |
| 12.8 | 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 |
| 12.a | 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 |
| 12.b | 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 |
| 12.c | 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。 |
出典:SDGグローバル指標(SDG Indicators)|外務省
SDGs目標12のターゲットには、2030年までの達成を目指している目標が数多く含まれています。2030年までに目標を達成するには、世界中の国や企業、個人が問題解決に向けて積極的に取り組む必要があるでしょう。
SDGs「つくる責任つかう責任」に対する企業の取り組み事例5選
SDGs「つくる責任つかう責任」に対する企業の取り組み事例として、5つの有名企業をご紹介します。
- LEGO
- Apple
- ユニクロ
- メルカリ
- セブン&ホールディングス
SDGs「つくる責任つかう責任」の目標達成に向けて、世界中の企業がさまざまな取り組みを行っています。企業の取り組みを知ることで、自身の職場でできることが具体的にイメージしやすくなるでしょう。
各企業の取り組みを詳しく解説します。
1.LEGO
デンマークの玩具メーカー「LEGO(レゴ)」は、SDGs「つくる責任つかう責任」に積極的に取り組んでいる企業です。SDGsが国連で採択された2015年には、すべてのレゴパーツを2030年までに持続可能な材料で製造するという目標を掲げました。
2023年9月のレゴグループによるニュースリリースでは、SDGsに対する取り組みや目標について詳しく記載されています。
発表された内容の一部は次のとおりです。
- 私たちは製品とビジネスをより持続可能なものにすることにこれまで以上に取り組んでいます。
- 2025年までの4年間で、持続可能性への取り組みへの支出を3倍の14億ドルに増やす予定です。
- 当社は、2032年までに、より持続可能で循環可能な素材を使用して製品を製造するよう取り組んでいます。
- 当社は、2032年までに炭素排出量を37%削減するという目標を設定し、長期的には 2050年までに炭素排出量を実質ゼロにすることを約束しています。
- 当社は持続可能な素材への投資にも力を入れています。
引用:The LEGO Group remains committed to make LEGO® bricks from sustainable materials|LEGO(Google翻訳による翻訳)
ニュースリリースでは、上記の内容とともに再生ペットボトルを使用したレゴブロックの製造を断念すると発表されました。断念した理由は、2年間ものテストを経て、二酸化炭素排出量の削減に役立たないという判断がされたためです。
レゴグループはこれからも、資金や労力を投入して持続可能な素材の開発に挑戦します。
2.Apple
SDGs「つくる責任つかう責任」に積極的に取り組んでいる企業の一つに、アメリカのIT企業である「Apple」があります。Appleは、2030年までにすべての製品をカーボンニュートラルにする目標を掲げています。
まず、「カーボンニュートラル」とは以下のとおりです。
“温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します”
Appleは素材や電力、輸送において革新的な手法を用い、炭素排出量の大半を削減しています。また、削減しきれない分を相殺するため、世界中の自然を活用したプロジェクトに対して投資を行っています。
Appleが取り組む計画の進捗状況は以下のとおりです。(2024年1月時点)
| 素材 | 2022年に出荷した製品に再生素材と再生可能な素材が占める割合は、
すべての素材の20%でした。 |
| 製造 | 300社以上のサプライヤーが、2030年までにAppleの全製品の製造に100%再生可能電力を使うことを確約しています。これはAppleの直接製造費支出先の90%以上に相当します。 |
| 輸送 | Appleの輸送計画により、HomePod(第2世代)の輸送時の炭素排出量を80%削減しました。 |
| 製品の使用 | 2008年以来、製品による平均エネルギー消費量が70%以上減少しました。 |
| 回収 | 2022年には、40,000トンを超える電子廃棄物をリサイクルしました。 |
Appleでは、2030年の目標に向けて、素材・電力・輸送の3大排出源を中心に、積極的な取り組みが行われています。
3.ユニクロ
日本のアパレル企業である「ユニクロ」は、SDGs「つくる責任つかう責任」に積極的に取り組む企業の一つです。
SDGs「つくる責任つかう責任」に関する代表的な取り組みの一つに「RE.UNIQLO」があります。
「RE.UNIQLO」とは、服から服へのリサイクルを目指し、ユニクロの全商品を対象にリサイクル、リユースする取り組みです。
「RE.UNIQLO」の一環として、服を必要としている世界中の人々に届ける取り組みが行われています。2022年8月までの累計として、80の国や地域に5050万点もの衣料支援が行われました。
4.メルカリ
SDGs「つくる責任つかう責任」に積極的に取り組む企業の一つに、フリマアプリを運営する「メルカリ」があります。メルカリは、SDGsが国連で採択される以前から、ビジネスとして循環型社会の実現を目指している企業です。
ビジネスとしてSDGsを実践することについて、株式会社メルカリブランドマネージャーの田原純香さんは以下のように述べています。
“メルカリは「フリーマーケット(フリマ)アプリ」ですが、誰かにとって不要なものが、別の誰かにとっては価値のあるものになる社会の実現をめざし、ビジネスを展開しています。”
引用:「メルカリらしさ」を大切に、循環型社会の実現をめざす 企業のSDGs取り組み事例 Vol.7(前編)|講談社SDGs by C-station
メルカリは、事業の成長がそのまま環境問題の解決につながり、SDGsへの取り組みになるマーケットプレイスと言えるでしょう。
5.セブン&アイ・ホールディングス
世界中で事業を展開する「セブン&アイ・ホールディングス」は、SDGs「つくる責任つかう責任」に積極的に取り組む企業です。環境問題に対して「GREEN CHALLENGE 2050」を宣言し、グループ全体でさまざまな取り組みを行っています。
GREEN CHALLENGE 2050は、事業活動による環境への負荷が大きい4つの分野を定めました。4つの分野に対する主な取り組みや目標は以下のとおりです。
| CO2排出量削減 | |
| 取り組み例 |
|
| 2030年の目標 |
|
| プラスチック対策 | |
| 取り組み例 |
|
| 2030年の目標 |
|
| 食品ロス・食品リサイクル対策 | |
| 取り組み例 |
|
| 2030年の目標 |
|
| 持続可能な調達 | |
| 取り組み例 |
|
| 2030年の目標 |
|
同社のサステナビリティ推進部シニアオフィサーの釣流真由美さんは、今後のビジョンについて、以下のように述べています。
“SDGsの目標は私たちだけの力では決して成し遂げられません。私たちの取り組みを日々発信することで、共感していただける仲間を増やし、あらゆるステークホルダーの皆さまとともに豊かな地球と社会を次世代につなげていきたいと考えています。”
引用:暮らしに身近な社会課題をビジネスで解決するセブン&アイ・ホールディングスの挑戦 企業のSDGs取り組み事例vol.43|講談社SDGs by C-station
セブン&アイ・ホールディングスは、事業の成長に伴う環境への負荷を限りなく抑えるため、グループ全体での取り組みを強化し続けています。
SDGs「つくる責任つかう責任」に関する世界の現状

SDGs「つくる責任つかう責任」に関する世界の現状は、現在も多くの問題が残っているため、目標の達成は容易ではありません。
主な課題は以下の3つです。
- 食品ロス
- プラスチック廃棄物
- エネルギー消費
各項目の現状と問題点について解説します。
食品ロス
SDGs「つくる責任つかう責任」に関する課題の一つに、食品ロス問題があります。食品ロスとは、まだ食べられるにもかかわらず、ゴミとして廃棄されてしまう食品のことです。
食品ロスの現状として、世界で生産されている食糧生産量の3分の1にあたる13億トンが廃棄されています。これほどの量の食品が廃棄されている一方で、発展途上国の食料不足は解消されていません。
食品ロスが多ければ多いほど、運搬や焼却時に排出される二酸化炭素が増えます。二酸化炭素の排出は、直接的な自然環境の悪化につながるため、引き続き食品ロスを減らす努力が必要です。
当社のグループ会社である株式会社アザナでは、異業種連携による食品ロス軽減の取り組みが行われています。日本の企業による食品ロス軽減の取り組み例として、ぜひ参考にしてみてください。
参考:異業種連携によるフードロス軽減の取り組み|ブランディングテクノロジー
プラスチック廃棄物
SDGs「つくる責任つかう責任」に関する課題の一つに、プラスチック廃棄物の問題があります。プラスチック廃棄物とは、使用後に廃棄されたプラスチック製品や製造過程で生じる微粒子などのことです。
プラスチック廃棄物の量は依然として増加傾向であり、このままだと2050年には海洋生物よりも多くなると予想されています。
プラスチック廃棄物は焼却すると二酸化炭素が排出されるため、ゴミが増えるほど自然環境の悪化につながります。また、プラスチックは自然に還りにくい素材であるため、生産量を減らす努力が必要です。
エネルギー消費
SDGs「つくる責任つかう責任」に関する課題の一つに、エネルギー消費の問題があります。世界のエネルギー消費量は経済成長に伴い増加傾向であり、2020年には石油換算で133億トンに達しました。
このままのペースで世界のエネルギー消費量が増加すると、ほとんどの天然資源が100年以内になくなると言われています。
資源のほとんどを海外からの輸入に頼っている日本にとって、エネルギー消費の問題は深刻であり、早急な対策が必要です。
参考:第1節 エネルギー需給の概要等|経済産業省 資源エネルギー庁
SDGs「つくる責任つかう責任」達成のために私たちにできること
SDGs「つくる責任つかう責任」達成のためには、国や企業だけでなく個人の積極的な参加が不可欠です。以下に、私たちができる3つのことを紹介します。
- ゴミの削減に協力する
- 何を買うかよく考える
- 3Rを意識する
各項目に対する私たちの取り組みは、目標達成に向けた大きな力となるでしょう。
ゴミの削減に協力する
SDGs「つくる責任つかう責任」達成のためには、私たちがゴミの削減に協力する必要があります。個人でできるゴミの削減方法は、主に以下のようなものです。
- 食品アウトレットを利用する
- 使い捨て商品を繰り返し使えるものにする
- レジ袋の代わりにマイバックを利用する
- マイボトルを持ち歩く
- 外食の際は食べ切れる量を注文する
- ゴミをきちんと分別する
- 生ゴミを堆肥化する
目標を達成するには、一人一人ができることを積極的に実行する必要があるでしょう。
何を買うかよく考える
SDGs「つくる責任つかう責任」達成のためには、何を買うかよく考えてから購入することが必要です。
よく考えてから購入する理由は、生産者の「つくる責任」に対して消費者には「つかう責任」があるためです。
商品を購入する際の判断基準の一つに、環境ラベルの有無があります。環境ラベルは、資源や環境に配慮して生産された商品であることを示しているため、商品選びの目安となるでしょう。
消費者が環境ラベルのついた商品を選ぶことは、SDGs「つくる責任つかう責任」への貢献につながります。
3Rを意識する
SDGs「つくる責任つかう責任」を達成するために、私たちができることとして、3Rを意識することが挙げられます。3Rとは、リデュース(Reduce)・リユース(Reuse)・リサイクル(Recycle)のことです。
リデュース(Reduce)・リユース(Reuse)・リサイクル(Recycle)の意味は、以下のとおりです。
- リデュース(Reduce):ゴミを減らすこと
- リユース(Reuse):捨てずにそのままの形状で再利用すること
- リサイクル(Recycle):廃棄物を原材料やエネルギー源として再利用すること
3Rを意識した取り組みとして、マイバックやマイボトル、資源回収BOXの利用などがあります。また、古本屋やリサイクルショップの利用、フリマアプリの活用なども効果的です。
3Rを意識することは、無駄なゴミを増やさず資源として活かすための重要な取り組みです。
SDGs「つくる責任つかう責任」の実現には企業の積極的な参加が不可欠
SDGs目標12の実現にはつくる側である生産者と、つかう側である消費者それぞれの責任について深く理解する必要があります。企業または個人として取り組むべき行動について、本記事で解説した内容を参考に活動をはじめてみてはいかがでしょうか?
その際に自身の企業や職場でSDGsに取り組み、ブランディングやマーケティングに活かしたいとお考えの方はぜひ一度、当社へご相談ください。当グループはこれまでSDGsに取り組んできた豊富な経験から、最適なサポートをご提供できます。
企業のブランディングやマーケティング構築に役立つ資料を無料で配布しています。顧客リサーチや業界研究から導き出したエビデンスをもとにノウハウが体系化されているため、ぜひご活用ください。
また、中小企業様ならではの課題に対し、目的や業界別にオンラインセミナーを開催しています。