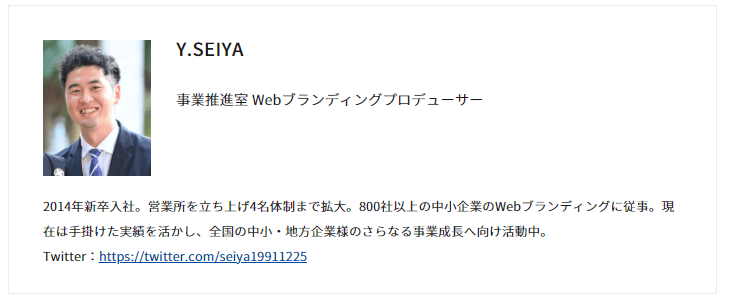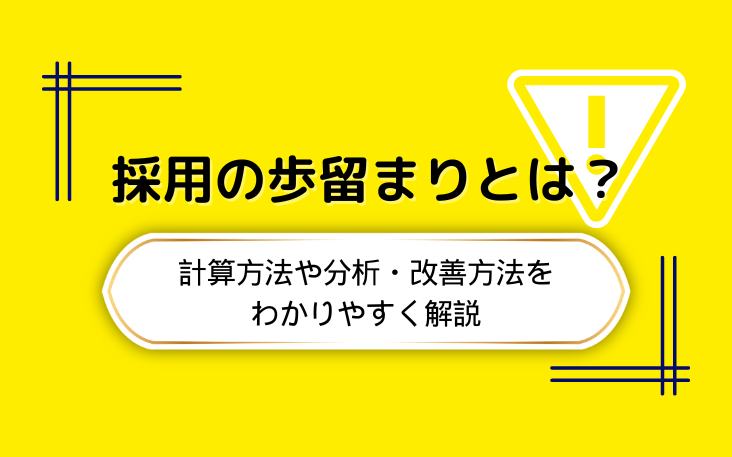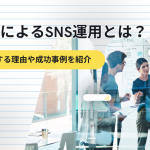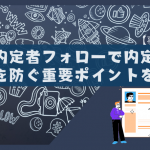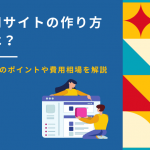「採用歩留まりを上げたい」
多くの人事担当者がそのように考えているのではないでしょうか。
採用歩留まりの低下は、多くの企業が直面する大きな課題です。
しかし、適切な改善策を講じることで、この問題は解決できます。
この記事では、採用歩留まりの計算方法や分析・改善方法をわかりやすく解説していますので、この記事で紹介する方法を実践し、採用歩留まりを向上させましょう。
この記事でわかること
- 採用歩留まりの計算方法と具体的な計算式
- 採用プロセスのどの部分に問題があるかを見つけるためのデータ分析手法
- 採用歩留まり改善のための具体的なアクションプラン
こんな人におすすめの記事です
- 人事担当者
- 採用マネージャー
- 中小企業の経営者
魅力的な採用サイトで優秀な人材をゲット!
目次 [show]
採用歩留まりとは?基本概念とその重要性

採用歩留まりとは、採用プロセスにおいて、特定の段階から次の段階に進む応募者の割合を示す指標です。
ここでは、
- 採用歩留まりの定義と重要性
- 新卒採用と中途採用の歩留まり平均
について、解説していきます。
採用歩留まりの定義と重要性
採用歩留まりは、採用活動の効率性や効果を評価するために用いられます。
採用歩留まりを計算することで、どの段階で応募者が多く離脱しているのか、どの段階が最も効果的かを把握できます。
採用歩留まりは、企業の採用プロセス全体の効率性や効果を測るための重要な指標です。
以下にその理由を挙げます。
採用歩留まりの重要性
- 採用プロセスの改善
歩留まり率が低い段階を特定することで、どの部分に改善が必要かを明確にできます。例えば、一次面接で多くの応募者が離脱している場合、その面接の方法や内容を見直すことで改善が期待できます。 - データに基づく意思決定
採用歩留まりのデータを定期的に収集・分析することで、データに基づく意思決定が可能になります。感覚や経験に頼ることなく、具体的なデータを基に改善策を講じられるため、より精度の高い採用戦略を立てられます。
新卒採用と中途採用の歩留まり平均
新卒採用の歩留まり平均
2023年度の新卒採用における歩留まり平均は約50%です。
この数字は、エントリーから書類選考、書類選考から面接、面接から内定といった各段階での進行率を総合的に見た平均値です。
(参考サイト)リクルート就職白書2023
中途採用の歩留まり平均
一方、中途採用の歩留まり平均は非常に高く、92.1%に達しています。
これは、中途採用における内定辞退率が比較的低く、内定承諾率が高いためです。
中途採用の応募者は、目指す業界や職種が明確であることが多く、企業への入社意欲も高いため、歩留まりが高い傾向にあると言えるでしょう。
(参考サイト)マイナビ中途採用状況調査2023年版
魅力的な採用サイトで優秀な人材をゲット!
採用歩留まりの計算方法と例
採用歩留まりの計算式を活用することで、採用プロセスの各段階における効率性を評価し、改善点を見つけられます。
ここでは、
- 採用歩留まりの基本的な計算式
- Excelを使った採用歩留まり計算方法と例
について、解説していきます。
採用歩留まりの基本的な計算式
採用歩留まりの基本的な計算式は、以下の通りです。
採用歩留まりの基本的な計算式
- 書類選考通過率
計算式:
書類選考通過率 = (書類選考通過者数÷書類選考受験者数) × 100
例:
100名が書類選考を受け、そのうち70名が通過した場合、書類選考通過率は70%です。
(70÷100) × 100 = 70 - 面接通過率
計算式:
面接通過率 = (面接通過者数÷面接受験者数) × 100
例:
50名が一次面接を受け、そのうち30名が通過した場合、一次面接通過率は60%です。
(30÷50) × 100 = 60 - 内定承諾率
計算式:
内定承諾率 = (内定承諾者数÷内定出し数) × 100
例:
10名に内定を出し、そのうち6名が承諾した場合、内定承諾率は60%です。
(6÷10) × 100 = 60
採用プロセス全体での歩留まり率を求める場合は、各段階の歩留まり率を積算して計算することもあります
総合歩留まり計算式の例
総合歩留まり率 = (最終合格者数÷総応募者数) × 100
例:
1000名が応募し、最終的に100名が内定承諾に至った場合、総合歩留まり率は10%です。
(100÷1000) × 100 = 10
Excelを使った採用歩留まり計算方法と例
採用歩留まりを計算するために、Excelを活用する方法を紹介します。
各段階での応募者数や通過者数などのデータを入力し、歩留まりの計算部分は以下のような数式にて算出できます。
| A | B | C | D | |
| 1 | フェーズ | 応募者数 | 通過者数 | 歩留まり率 |
| 2 | 応募 | 100 | 90 | 応募通過率 (C2/B2)*100 =90% |
| 3 | 書類選考 | 90 | 70 | 書類選考通過率 (C3/B3)*100 =77% |
| 4 | 一次面接 | 70 | 40 | 一次面接通過率 (C4/B4)*100 =57% |
| 5 | 最終面接 | 40 | 20 | 最終面接通過率 (C5/B5)*100 =20% |
| 6 | 内定 | 20 | 15 | 内定率 (C6/B6)*100 =75% |
| 7 | 内定承諾 | 15 | 10 | 内定承諾率 (C7/B7)*100 =66% |
| 8 | 全体積算 | 100 | 10 | 総合歩留まり率 (C8/B8)*100 =10% |
魅力的な採用サイトで優秀な人材をゲット!
採用歩留まりが低下する原因と分析
採用歩留まりの低下には様々な要因が関与しており、それぞれの原因を詳細に分析することで、具体的な改善策を講じられます。
ここでは、採用歩留まりが低下する原因として、
- 内定スピードの差と他社との競争
- 不十分な採用ブランディングとSNSの影響
- 応募者・内定者へのフォロー不足
について解説し、その分析手法を説明します。
内定スピードの差と他社との競争
内定スピードの差
- 内定スピードの遅さ:
採用プロセスが長引くと、優秀な応募者が他社の早い内定を受けてしまう可能性が高まります。応募者は、複数の企業からオファーを受けることが一般的で、早い段階で確定的なオファーをもらった企業を選ぶ傾向があります。 - 意思決定の遅延:
企業内部での意思決定プロセスが遅れると、内定の通知も遅れがちです。これにより、応募者が他の迅速に動く企業に流れてしまいます。 - 分析手法:
プロセスの時間計測:
採用の各段階(応募受理、書類選考、面接、最終面接、内定通知)にかかる時間を計測します。これにより、どの部分で時間がかかっているかを明確にします。
応募者フィードバック:
内定を辞退した応募者に対して、辞退理由を調査します。特に「内定スピード」についてのフィードバックを集め、改善点を特定します。
他社との競争
- 競争激化:
同じ優秀な応募者を狙っている企業が多い場合、他社との競争が激化します。特に人気の高い業界や職種では、企業間での争奪戦が繰り広げられます。 - オファー内容の差:
他社がより魅力的なオファー(給与、福利厚生、キャリアパスなど)を提示している場合、応募者はそちらを選ぶ傾向があります。 - 分析手法:
市場調査:
競合他社の採用プロセスやオファー内容を調査します。給与水準、福利厚生、働き方の柔軟性など、他社の強みを把握し、自社と比較します。応募者データの分析:
自社に応募した者の中で、どの程度が他社に流れているかを分析します。特に、どのタイミングで他社に流れたのかを特定し、原因を探ります。
不十分な採用ブランディングとSNSの影響
不十分な採用ブランディング
企業の魅力やブランドが十分に伝わっていない場合、応募者が他の魅力的な企業に流れてしまいます。
- 分析手法
応募者に対して企業の魅力をどう感じたかを調査し、他社と比較します。また、採用ページや求人広告のアクセス数を解析し、応募者の反応を測定します。
SNSの影響
SNSや口コミサイトで企業のネガティブな情報が広がっている場合、それが応募者の意思決定に影響を与えます。
- 分析手法
SNSや口コミサイトをモニタリングし、自社に対する評価を定期的にチェックします。また、ネガティブなコメントが多い場合、その具体的な内容を分析し、改善策を検討します。
応募者・内定者へのフォロー不足
応募者フォロー不足の影響
応募者へのフォローが不足していると、応募者は企業に対して不信感を抱いたり、興味を失ったりする可能性が高まります。
特に、応募から面接、内定通知までの間に適切なコミュニケーションが取れていない場合、応募者は他社のオファーを受け入れる可能性が高くなります。
具体的な影響
- 不安感の増大:
進捗状況が不明確なまま放置されると、応募者は不安を感じます。 - 企業イメージの低下:
コミュニケーション不足は、企業の印象を悪くし、ブランドイメージにも悪影響を与えます。 - 辞退率の上昇:
フォローが不十分な場合、内定を辞退する応募者が増えます。
内定者フォロー不足の影響
内定者へのフォローが不足していると、内定承諾率が低下し、内定辞退が増加します。内定通知後、入社までの期間に適切なフォローがないと、他社のオファーに流れたり、入社意欲が低下したりします。
具体的な影響
- 内定辞退の増加:
入社前の不安や疑問が解消されないまま放置されると、内定者は他の企業に流れる可能性が高まります。 - エンゲージメントの低下:
入社前のフォロー不足は、エンゲージメントやモチベーションの低下を招きます。
採用歩留まりを改善するための具体策

採用歩留まりを改善するための具体策は、採用プロセス全体の効率を向上させ、優秀な人材の確保につながります。
ここでは、
- 採用サイトの最適化
- 採用フローの短縮化と柔軟な面接対応
- 動機形成の強化と内定者フォローの強化
について、解説していきます。
採用サイトの最適化
採用サイトは、応募者が企業に対する第一印象を形成する重要な接点です。
以下に、採用歩留まりを改善するために採用サイトを最適化する具体的な方法を紹介します。
採用サイトを最適化する具体的な方法
- 魅力的な企業ブランディング
高品質なビジュアル:
企業のオフィス環境、社員の活動、社内イベントの写真や動画を掲載し、視覚的に魅力的なサイトを作ります。
企業ストーリーの紹介:
企業の歴史、ビジョン、ミッションを具体的に紹介し、応募者が共感できるようにします。
社員インタビュー:
現場で働く社員のインタビューや成功事例を掲載し、リアルな職場の雰囲気を伝えます。
社員ブログや動画:
社員が執筆するブログや動画コンテンツを公開し、企業文化をアピールします。
- コンテンツマーケティング
定期的なブログ更新:
採用関連のトピックや業界ニュースなどを定期的にブログで発信し、サイトの新鮮さを保ちます。
ソーシャルメディア連携:
SNSと連携し、採用サイトへのアクセス数を増加させます。
採用フローの短縮化と柔軟な面接対応
採用フロー短縮化の具体策
冗長なプロセスの削減:
不必要な選考プロセスを排除し、シンプルなプロセスにします。
例えば、初期段階での複数回の面接を1回にまとめるなどです。
オンライン選考の導入:
書類選考や初期面接をオンラインで実施し、応募者の移動時間やコストを削減します。
結果通知のスピードアップ:
各選考プロセスの結果を迅速に応募者に通知します。
これにより、応募者の不安を軽減し、次の選考への意欲を高めます。
事前スケジュールの設定:
面接官のスケジュールを事前に調整し、応募者が面接をスムーズに受けられるようにします。
これにより、面接の間隔を短縮し、全体のプロセスをスピードアップします。
柔軟な面接対応の具体策
リモート面接の活用:
初期段階や地方在住の応募者に対して、オンライン面接を積極的に活用します。これにより、応募者の移動の負担を減らし、より多くの応募者に対応できます。
多様な時間帯の設定:
平日夜間や週末の面接オプションを提供し、応募者のスケジュールに合わせた面接を実施します。これにより、現職中の応募者や多忙な応募者にも対応できます。
一貫した評価基準の適用:
面接官に対して、統一された評価基準と適切な面接技術を習得させるトレーニングを実施します。これにより、応募者に対する一貫した対応が可能となり、評価のばらつきを防ぎます。
動機形成の強化と内定者フォローの強化
動機形成の強化具体策
魅力的な企業ストーリーの伝達:
企業のビジョンやミッションを明確に伝え、応募者が企業の未来に対して共感しやすくします。企業の成長ストーリーや社会的なインパクトを強調することで、応募者の興味を引きます。
リアルな社員インタビュー:
現場で働く社員のインタビューやキャリアパスの成功事例を共有し、応募者が自分の将来を具体的にイメージできるようにします。
具体的な業務内容の説明:
面接や説明会で具体的な業務内容や期待される成果を詳細に説明します。応募者が入社後の業務を具体的にイメージできるようにすることで、動機付けを強化します。
内定者フォローの強化具体策
進捗報告と連絡の維持:
内定者に対して定期的に連絡を取り、進捗状況や入社準備に関する情報を提供します。メールや電話、チャットツールを活用し、コミュニケーションを途切れさせないようにします。
内定者へのメンター割り当て:
内定者一人ひとりにメンターを割り当て、個別のサポートを提供します。メンターが入社前から相談に乗ることで、内定者の不安を解消し、エンゲージメントを高めます。
カジュアルな交流イベント:
内定者同士や現場社員とのカジュアルな交流イベントを実施し、入社前にチームメンバーと親交を深める機会をつくります。
まとめ:採用歩留まりを理解し改善する
採用歩留まりを理解し、改善することは、企業の採用活動の成功に直結します。
効率的な選考プロセス、柔軟な対応、効果的な動機形成、そして内定者フォローを強化することで、採用プロセス全体の効率を向上させ、優秀な人材を確保できます。
これらの具体策を実践し、より効果的な採用活動を目指しましょう。
【らしさを発信⇒採用率を高める】採用サイト制作サービスのご案内
当社では狙った人材を獲得するための採用ブランディングとオリジナル採用サイト制作を掛け合わせた「【らしさを発信⇒採用率を高める】採用サイト制作サービス」を提供しています。自社のブランドを効果的に高めながら優秀な人材を獲得するため採用サイトの制作をお考えの方は、ぜひ当サービスをご利用ください!
このような方向けのサービスです
- 自社の魅力が求職者に理解されない…
- 入社後のミスマッチが原因ですぐに辞めてしまう…
- 求める人材が来ない…
- 応募者が少なく、面接まで至らない…
無料相談・お問い合わせ